今週のコラム 6月16日
コロナ時代の健康教育 大友奈緒
入学式を前に、一斉休校となった昨年度は、戦後教育の中でも、誰も経験したことのない異例の学校生活となりました。新しい感染症に関する確かな情報がない中で、児童生徒の安全・安心を守ることが学校の宿命でした。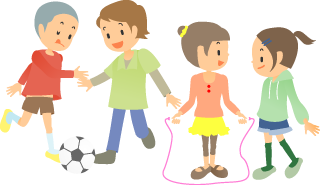
1 心と体はつながっている
「自粛」「スティホーム」のアナウンスの中で、一番難しかったのは子供たちが生活リズムを整えることでした。健康な心と体があってこそ「知りたい、学びたい、話したい」という学習意欲が喚起されることを実感しました。
2 ゼロリスクのリスク
登校してから誰とも話をせず、接触をしなければ、感染のリスクは減ります。徹底的に消毒すればさらに感染リスクは減りますが、できることも減ってしまうのです。リスクを一面から捉えず、バランス感覚を大切にすることが、学校の健康を保つことになるという思いを強くしました。
3 目の前のできることに焦点を
合言葉は「目の前のできることに焦点を併せて進む」でした。今できる最善を尽くし、今を積み重ねていくことが、心の健康を保つことになると考えています。
(2021.6.16) 全文はこちらをご覧ください
大友先生のコラム 加賀谷 孝
先週は種村千智先生(中学校養護教諭)の『つながりで支えあう健康』がコラムに掲載されました。 今週は、大友奈緒先生(小学校教頭)が『コロナ時代の健康教育について』を掲載しました。両先生ともコロナの対応を述べております、視点を変えての対応ですので興味深い内容でした。今週の大友先生は「自粛」「ステイホーム」のアナウンスの中で、一番難しかったのは、「子どもたちが生活リズムを整えることであった」と述べています。好きなゲームを続けても「友達に会いたい」という感情をうめることはできませんでした。「子どもたちがいてこその学校だ」と感じた臨時休業明けの6月でした。
また、感染症予防に努めるために、職員の共通理解が必要でした。合言葉は『目の前のできることに焦点をあわせて進む』でした。管理職としての視点も見えますが、根底には学校教育は子ども中心であり職員が一丸となって進まなければ、心と身体の健康が保てないとの提案であったように思います。
ホームページを御覧の皆様はどのように考えますか。
(2021.6.16)
