今週のコラム 6月22日
家庭人を育てる 沼澤 賢
私は、コロナ禍における教育課程の改善策を考えてみました。 その1 通知表は子供自らがつける。
その2 家庭人を育てるために「自炊の日」を設定する。
その3 第1次産業体験を3泊〜5泊で行う。
その4 朝の時間に「問いの時間」を設定する。
その5 高学年の教科担任制と全学年単元交代制を行う。
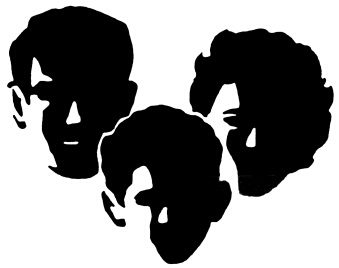
自分で「家庭人」という言葉をつくってみました。外に向かう「社会人」に対して、もっと内側を見てもいいのではないか、もっと家の中に光を当てることが大切ではないかと思ってつくってみました。このコロナ禍で、「外」に出る前に、自分の生活の基盤となる「内」=「家庭」が脆弱になっているのではないでしょうか。だからこそ、「外」も「内」も抱え込み、包摂するものとしての学校が大事であると考えています。
(2021.7.8) 全文はこちらをご覧ください
沼澤先生のコラム 加賀谷 孝
今週は、沼澤 賢先生(小学校教務主任)が『コロナ禍で考えたこれからの教育課程』をテーマに掲載しました。沼澤先生は、視点がとてもユニークであり、どの内容も挑戦してみたくなる内容ばかりです。教育課程の位置づけが、教育活動全般の基幹になると述べています。教務主任(校務分掌)という立場からも、教育課程編成の重要性を改めて認識し、教育活動全般の改善・改革に努めようとしています。
自己評価の活用では、通知表の評価は、自己評価とする。子ども自らが、評価することで単元内容の再確認が必要になること。通知表に表記されている「思考力とは?」、「創造性とは?」を子どもたちなりに考える機会としたい。
家庭人を育てるでは、自炊の日の設定を推奨したいと述べています。コロナ禍で、子どもたちも含め、家族が家庭内で過ごすことが多くなりました。このことを機会に家庭や家族について考えさせたい。
問いを持てる人間の育成では、「問いの時間」を設定し、不思議に思っていることや、疑問を発表したり、友達と話し合ったりする時間を大切にしたいと考えています。
レポートの結びで学校は、「可能性に満ちたところ」「家庭人を育てるところ」「問いを持つところ」「仲間と話し合うところ」と結んでいます。
「子どもたちの可能性を引き出す」教育課程を先生たちと話し合って編成することと思います。 ホームページをご覧の皆様はどのように考えますか。
(2021.7.8)
