今週のコラム 8月1日
八千代から新たな学校創造 種村 保
中央教育審議会の答申において,令和の日本型学校教育の構築に向けた様々な提言が出されました。その中の一つに「義務教育9年間を見通した教科担任制の在り方」という提言があり,2022年度を目途に小学校高学年から,外国語や理科,算数などの教科における教科担任制の導入が明記されています。このことからも,これからの義務教育においては小学校と中学校が形式的に連携をするのではなく,小中学校の全職員が一つになって,児童生徒を9年間かけて育てる教育が必要になるという意識に転換することが必要であると考えます。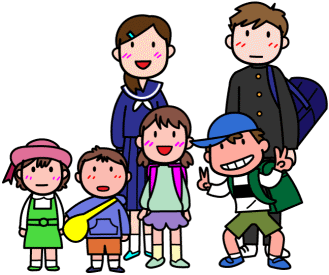
本市では,令和4年4月に施設一体型小中一貫校(義務教育学校)が開校します。一つの校舎で,一つの職員集団で,そして9年間を見通した指導が可能な学校だからこそできる取り組みは,たくさんあります。自然豊かな地域の環境や歴史ある地域の教育力を生かしながら,様々な行事や毎日の清掃活動,部活動や生徒会活動などを通して,多様な考えに触れたり,切磋琢磨する機会を確保したりしていきたいものです。 教職員,保護者,地域が一体となって力を合わせ,みんなで地域の子供たちを育てていくような,温かい義務教育学校を創りたいと思っています。
(2021.8.1) 全文はこちらをご覧ください
種村保先生のコラム 加賀谷 孝
今週は、種村 保先生(中学校教頭)が『小中一貫』~八千代から新たな学校創造~をテーマに掲載しました。八千代市で次年度開校予定の小中一貫校について述べております。小中学校間の連携の重要性は、広く認識されており、地域の実態に合わせ様々に取り組んでいますが、目標や活動の指針を明確にすることに苦慮しているのが現状であるように感じています。
種村先生は中央教育審議会の答申において、令和の日本型学校教育の構築に向けた提言から、「義務教育9年間を見通した教科担任制の在り方」で、2022年度を目途に小学校高学年から、外国語や理科、算数などの教科における教科担任制が導入されることに着目し、小中学校の全職員が一つになって、児童生徒を9年間かけて育てる意識に転換する必要があると述べています。
小中一貫校(義務教育学校)設立には多くの課題もありますが、地域社会の方々の理解を得ながら、目標を明確にし、学校教育の在り方を変革し、地域社会及び世界から注目される学校になることを期待します。 ホームページをご覧の皆様はどのように考えますか。 (2021.8.1)
