今週のコラム 8月8日
新たな教育に向けての提言 鈴木 利明
最近の状況をみると,発達障害を含めた特別な支援を必要とする児童,生徒の数は年々増加する傾向にあります。特別な支援を要する児童一人一人のおかれている状況を理解し,それぞれの教育的ニーズに応じた適切な指導,支援を行っていくためには,教職員の特別支援教育に関する専門性を高め,知識や指導力を向上させていくことは不可欠です。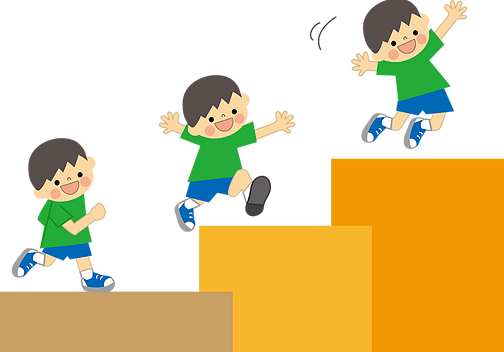
しかし,現在の学校,教職員がおかれている状況を考えると様々な業務に追われ,時間がないことも事実です。長期的な視野をもって,特別支援教育に関する専門性と高めていくことと同時に,教職員の負担を少しでも軽減していくために働き方改革,業務改善を行っていく必要があります。現在,国では小学校での35人学級の導入を段階的に実施していくことが決定していますが,更に一学級あたりの在籍児童の人数を減らしていくことや小学校にもスクールカウンセラーを配置すること,複数担任制を導入すること,外国籍の児童,保護者の対応が常時可能な人材を市教委等に配置することなどの措置も必要だと感じています。
特別支援教育を更に充実させ,一人一人の児童生徒の可能性を見つけ,伸ばしていくために,やるべきことはまだまだたくさんあるなと感じています。
(2021.8.8) 全文はこちらをご覧ください
鈴木先生のコラム 加賀谷 孝
今週は、鈴木利明先生(小学校校長)が『特別支援教育』をテーマに掲載しました。 鈴木先生は、最近の状況として特別な支援を必要とする児童、生徒の数は年々増加する傾向にあり、毎年のように特別支援学級等が新設、増設されていると述べております。
増加傾向の中でいくつかの課題を提示しております。〇 特別支援教育に携わる教職員の専門性が十分ではない。
〇 特別な支援を要する児童、生徒は通常学級にも在籍することから、全ての教職員 の特別支援教育に関する知識や指導力を向上させる必要がある。
具体的な取り組みでは、
〇 特別支援教育推進委員会の設置。
〇 研修会の充実。
〇 ユニバーサルデザインを意識した教室環境の整備。
新たな教育に向けての提言では、
一学級あたりの在籍児童数の削減、スクールカウンセラーの配置、複数担任制、外国 籍児童生徒の保護者への対応職員の配置等ですが、今後とも教育委員会との協議が必要な内容です。
特別支援教育を更に充実させ、一人一人の児童生徒の可能性を引き出し伸ばしていくために、やるべきことはまだまだたくさんあると述べています。
ホームページをご覧の皆様はどのように考えますか。 (2021.8.8)
