今週のコラム(第17回) 9月23日
教科担任制の導入 野木 雅生
私は「学級担任制」を否定する気は全くありません。「学級担任制」によって大きく成長できた子どもたちは多くいたと考えますし,確かな児童理解の目をもてるようになった教師も多く存在していると考えます。文部科学省も「学級担任制」の良さを認識しているため,低学年と中学年は「学級担任制」を継続するのだと考えます。一方で,高学年において「教科担任制」を導入することで教育の可能性が広がるのではないかと考えています。子どもたちが専門的な知識を身に付けることができたり,円滑に中学生活に馴染むことができたりすることで,児童が今までよりもさらに大きく成長できるかもしれません。
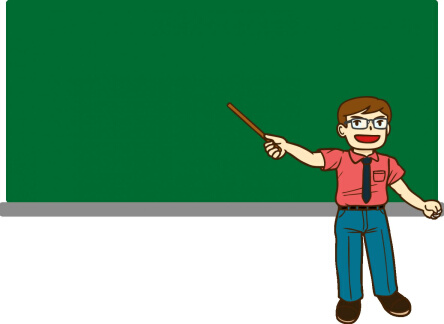
小学校教師にとっては「教科担任制」の導入を大きな変化だと感じられる方も少なからずいらっしゃると思います。物事を変化させるということは,勇気がいることで,時には大きな負担になることがあります。しかし変化がなければ,何事も変わりません。そして,大きな変化は大きなチャンスにもなり得ると思います。
私は日々学び続け,教師として子どもたちの成長のために,大きな変化を大きな成果につなげられるように,変化を楽しみながらチャレンジしていく教師でありたいと決意しています。
(2021.9.23) 全文はこちらをご覧ください
野木先生のコラムについて 加賀谷 孝
今週は、野木雅生先生(教育委員会指導主事)が『小学校における教科担任制の導入』をテーマに掲載しました。 2021年1月26日の中央教育審議会の答申に小学校高学年の教科担任制の本格導入が示されたことから、教師一人一人が教科担任制の意味をしっかり理解しなければならないと述べております。
学級担任制と教科担任制を比較して述べている文章を教育雑誌等で目にすることがありますが、教科担任制を実施したから学級担任の存在がなくなるということはないように思います。現在の中学校でも教科担任と学級担任は存在します。子どもたちは、学級担任の先生と教科担任の先生の役割を分けて見ているように思います。おそらく小学校でも高学年の子どもたちは自然にそのような見方になるのではないでしょうか。
課題は、学級担任として永らく小学校教員を経験した先生たちが、役割を自覚し教育活動に取り組めるかどうかだと思います。野木先生が述べている通り、教師一人一人が子ども目線で学級担任の役割と教科担任の役割を自覚できるかが課題解決の一つの視点だと思いますし、活発な議論が必要であるとともに、保護者・地域社会の理解も必要になると思います。
ホームページをご覧の皆様はどのように考えますか。
(2021.9.23)
