今週のコラム(第25回) 11月23日
少人数指導と少人数学級の効果 逢坂 誠
少人数指導および少人数学級の成果として、生徒理解をしやすくするとともに、きめこまやかな指導ができるようになっています。また、教師が生徒に寄り添って丁寧な指導をすることで、生徒一人一人に自己存在感を与えることができます。このことは、現在、八千代の教育の柱となっているSDGsの理念「誰ひとり取り残さない(No one will be left behind)」と同等で、本校としても大切にしています。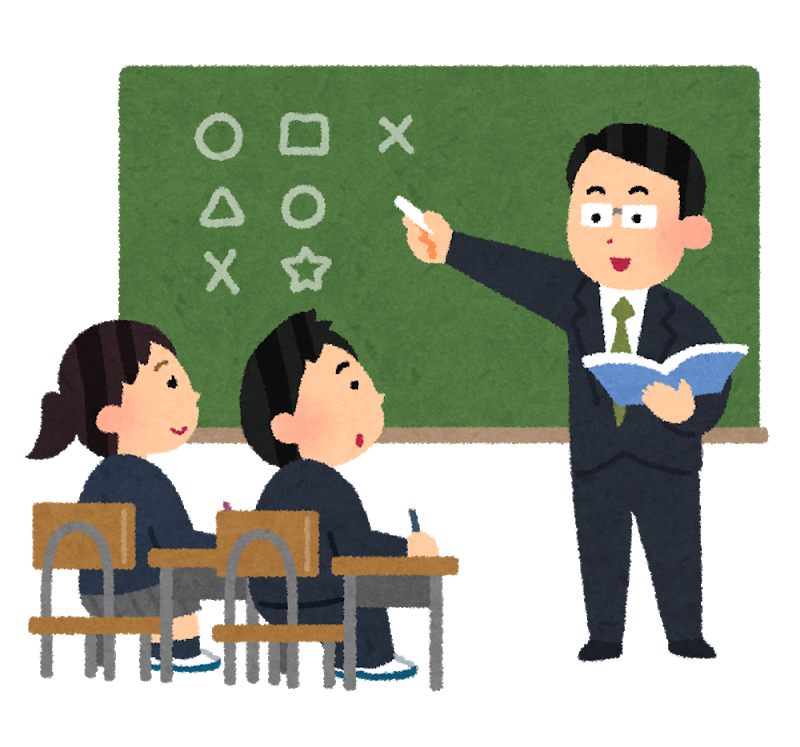
一方で課題は、現在、講師が不足している状況下であり、大学生の教員志望が減少傾向となっています。少人数指導及び少人数学級を実現するために、教員を増やすことが必要です。中学校においても「35人学級」を実現。そして、35人よりも少ない人数を目指していく必要があります。また、できるだけ多くの教科で少人数指導を実践していくべきだと考えています。
以上のことから、人材の確保が重要であり、向こう10年先の未来で少人数指導や少人数学級の実現ができるように、今できることを子供たちのために実践していくことが大切ではないでしょうか。
(2021.11.23) 全文はこちらをご覧ください
逢坂先生のコラムについて 加賀谷 孝
今週は、逢坂誠先生(中学校教頭)が『少人数指導と少人数学級の効果』をテーマに掲載しました。国は、義務教育標準法を改正し2025年度までに段階的に「35人学級」を導入することを決定しました。
数学の授業における小人数指導の取り組みについて述べています。単純分割少人数指導と習熟度別少人数指導です。また、タブレット活用の効果についても述べています。
新たな教育に向けての提言では、中学校においても「35人学級」の導入を求めています。そのためには教員の確保が必要であり、教育系大学のインターンシップ制の導入を提案しています。
世界中すべてのことが大きな転換期にきているように思います。教育の位置づけも見直す必要があります。未来像を模索し先の見える教育活動を実践したいものです。
ホームページをご覧の皆様はどのように考えますか。
(2021.11.23)
